CONTENTS
私たちは、2007年創業18年900サイト以上の実績がある会社
当社ウェブサイトへようこそ!ホームページは制作する時代から、集客する時代へ。そして、現在では、集客した見込み客を育成する流れを作るのがホームページの役割です。制作・集客・育成に関するご相談はこちらからご連絡ください。
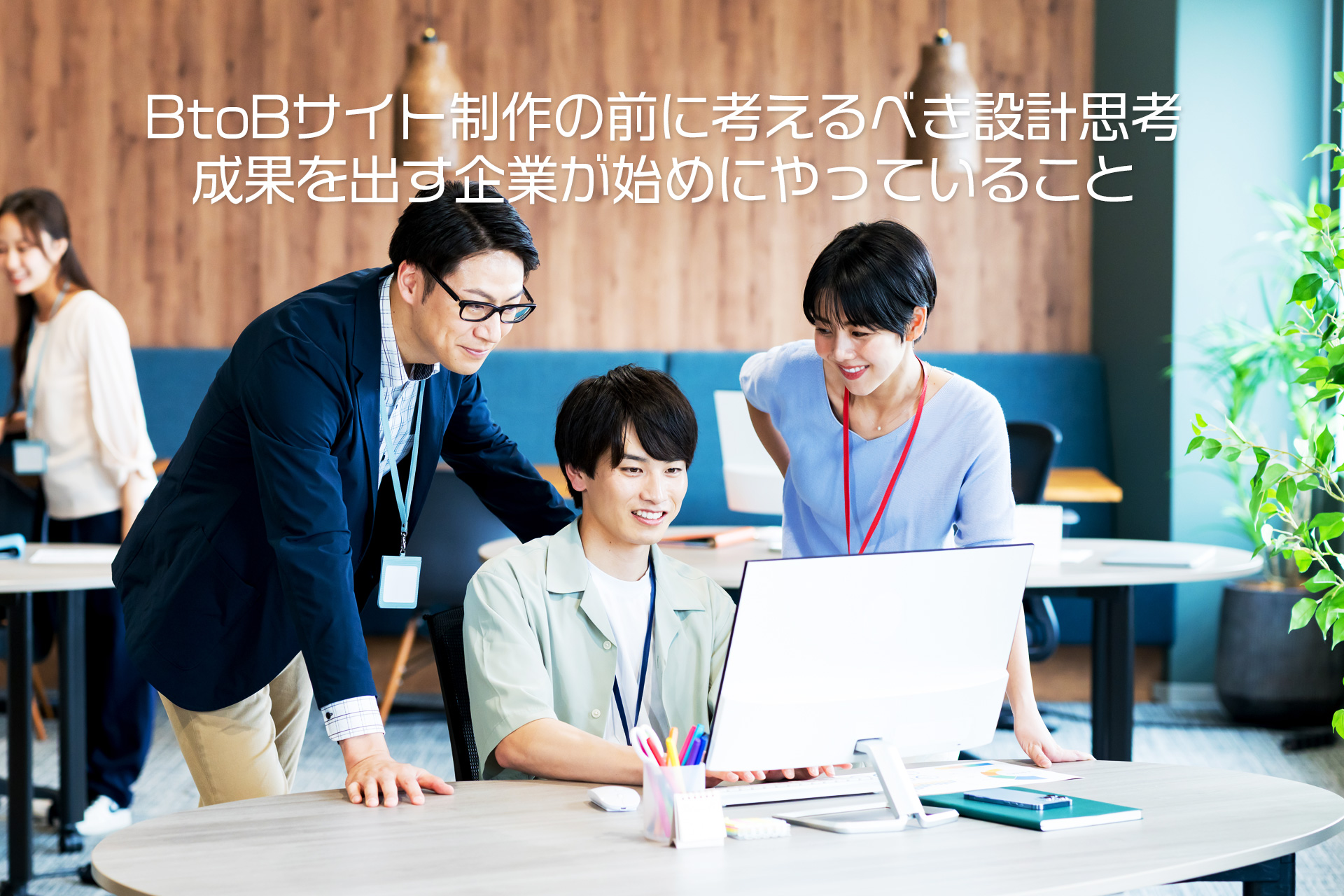
「ホームページをリニューアルしたけれど、思ったように問い合わせが増えない」
「営業資料として使えるサイトにしたいが、どこから手をつければ良いか分からない」
BtoB企業の経営者から、こうした相談をいただくことは少なくありません。
多くの企業が陥る共通の課題は、“制作前の戦略設計が十分に行われていない”ことです。
BtoBサイトは、デザインや見た目の美しさよりも、戦略的な設計思考(=誰に、何を、どう伝えるか)が成果を大きく左右します。
本記事では、BtoBサイト制作を多数手がけるグルコムが、制作前に経営者が必ず考えるべき5つの設計ステップを詳しく解説します。
多くのBtoB企業が、ホームページ制作を「会社情報を載せる」「見た目を整える」といった“作業的な工程”として捉えがちです。
しかし本来、ホームページは単なる情報発信ツールではなく、経営戦略・営業戦略の一部として機能させるべき“資産”です。
つまり、「見栄えの良いサイトを作ること」ではなく、“何を目的として・誰のために・どのように成果を出すか”という設計を行うことが、BtoBサイト成功の分かれ道となります。
たとえば、ある企業では「営業担当の負担を軽減したい」という目的で、よくあるFAQや資料ダウンロードページを充実させた結果、問い合わせ対応時間が大幅に削減されました。
また別の企業では、「展示会のフォローリードを増やしたい」という目的のもと、展示会名を含む特設ページを制作したところ、来場者からの問い合わせ率が2倍に向上しました。
このように、“目的の明確化”が設計の方向性を決める最初の鍵です。
営業効率化を目指すのか、新規顧客の開拓を重視するのか、既存顧客への情報提供を強化するのか——。
目的によって、ページ構成・導線設計・必要なコンテンツはまったく異なります。
反対に、戦略が曖昧なまま制作を始めてしまうと、完成後に「何を伝えたいのかがぼやけている」「問い合わせにつながらない」といった課題が浮き彫りになります。
デザインや文章がどれだけ洗練されていても、サイト全体に“目的の軸”がなければ、成果には結びつきません。
経営者としてまず取り組むべきことは、「このホームページで、どんな成果を出したいのか?」を明確に言語化することです。
これは単なる“制作依頼の前準備”ではなく、企業の方向性・強み・顧客との接点を整理する「経営的な棚卸し作業」とも言えます。
制作前の戦略設計は、企業のWeb戦略を“軸から整える”工程です。
この段階で目的・ターゲット・成果指標をしっかり定めることで、「制作後に後悔しない」「継続的に成果を出す」ホームページが実現します。
グルコムでは、制作前にクライアントと一緒に“経営課題とWeb戦略を結びつける”ディスカッションを重ねています。
その中で導き出された戦略こそが、後に問い合わせ増加・CVR向上・ブランド強化といった成果につながっているのです。
このように、制作前の戦略設計は、デザインやSEOよりも前に考えるべき“最も重要なプロセス”です。
経営者がこの意識を持つことで、ホームページは単なる「会社案内」ではなく、事業成長を支える“営業資産”へと進化します。
BtoBサイト制作を成功させるための第一歩は、「誰に」「何を伝え」「どう行動してほしいか」を明確に定義することです。
この3つの軸が曖昧なまま制作を進めてしまうと、いくらデザインや文章を整えても、成果につながりません。
ホームページは“誰かに何かを伝える”ための媒体です。
その“誰か”が明確でなければ、メッセージがぼやけ、訪問者の行動にもつながらないのです。
制作前の段階でこの3つを整理することは、戦略設計の土台をつくる最も重要なプロセスです。
それぞれの項目を、もう少し深く見ていきましょう。
まず最初に考えるべきは、「このサイトを訪れるのはどんな人か?」という問いです。
ここでの“誰に”とは、単なる業界や企業規模だけではなく、購買や意思決定に関わる具体的な人物像を指します。
たとえば、同じ製造業でも、
・技術部門の担当者は「品質・性能」を重視し、
・購買担当者は「コスト・納期」を重視し、
・経営者は「導入効果・信頼性」を重視します。
このように、役職や立場によって求める情報はまったく異なるのです。
したがって、「業界 × 企業規模 × 役職」でターゲットを細かく設定することが大切です。
たとえば:
・製造業 × 購買担当者
・建設業 × 経営層
・IT企業 × 管理部門責任者
このようにペルソナを設定することで、どんな言葉で、どんな順序で伝えるかが明確になります。
BtoBのホームページは、不特定多数ではなく、“特定の誰か”に深く刺さるサイト設計が成果を生むのです。
ターゲットを明確にしたら、次は「自社はその相手に対して何を伝えるのか」を整理します。
この“伝える内容”が、サイトの中核メッセージになります。
BtoBサイトでよくある失敗は、「自社の言いたいことだけを並べてしまう」ケースです。
訪問者が求めているのは、“自分の課題をどう解決してくれるのか”という視点です。
そのため、まずは顧客が抱えている課題を言語化し、それに対して「自社がどんな価値を提供できるか」をストーリーとして整理することが重要です。
具体的には、以下のようなメッセージ設計が効果的です:
「業界特化のノウハウで御社の課題を解決」
「中小企業でも導入しやすいコスト設計」
「スピード対応 × 品質保証で安心のサポート」
「全国対応・一貫体制でスムーズな取引を実現」
このように、“相手の課題”と“自社の強み”をつなぐメッセージを設計できれば、訪問者の共感を得やすくなります。
そのメッセージを軸に、トップページ・サービスページ・事例紹介ページの構成を考えることで、一貫性のあるサイトが完成します。
最後に重要なのが、「訪問者にどんな行動を起こしてほしいか」を具体的に定義することです。
BtoBサイトでは、購入ボタンやカートはありません。
その代わりに、“次のアクション(=コンバージョン)”をいかに自然に促すかが成果の分かれ目です。
典型的なコンバージョンの例としては:
・資料請求
・お問い合わせ
・事例ダウンロード
・セミナー申し込み
・製品カタログのダウンロード
などが挙げられます。
ただし、単にボタンを置くだけでは行動は起きません。
その前に、「今すぐ問い合わせたい」と思えるだけの“納得感と信頼”が必要です。
そのため、導線設計では次のような工夫が求められます。
・各ページ下部に“次の一手”を明示する(例:「詳しい資料を見る」「導入事例をもっと見る」)
・フォーム送信のハードルを下げる(例:「まずは無料相談」など)
・お問い合わせ前に「安心材料(FAQ・実績・導入事例)」を配置する
このように、訪問者の心理に沿った行動導線を設計することで、サイト全体が自然と成果を生む仕組みになります。
経営者がこの3つを明確に定義できれば、ホームページは単なる“情報掲載の場”ではなく、営業・マーケティングの両面で機能する強力なビジネスツールに変わります。
そして、この3軸の整理こそが、次の「導線設計」「SEO設計」などの具体的な制作工程のすべての土台となるのです。
BtoBビジネスの購買行動は、即決ではなく「調査・比較・検討」のプロセスを経ます。
したがって、ユーザーがどんな順番でサイトを見て、何を知りたいのかを設計することが不可欠です。
見込み客が「検索 → 訪問 → 比較 → 問い合わせ」に至るまでの一連の流れのこと。
この流れに沿ってページ構成を考えると、離脱を防ぎ、自然に“問い合わせ”へ導けます。
例:BtoB企業サイトの理想的な導線
・トップページ:価値訴求と信頼獲得
・サービスページ:詳細説明+導入効果
・事例ページ:実績による裏付け
・CTA(お問い合わせ・資料請求)
ホームページ制作というと、多くの企業が「デザイン」や「コピーライティング」に意識を向けがちです。
しかし、成果を生み出すBtoBサイトを作る上で最も重要なのは、“見た目”よりも“構造(サイト設計)”です。
どれほど美しいデザインでも、ページの構成や導線が整理されていなければ、ユーザーは必要な情報にたどり着けません。
結果として、滞在時間が短くなり、離脱率が上がり、検索エンジンからの評価も下がってしまいます。
逆に、情報の流れやページ階層が明確で、論理的に整理された構造を持つサイトは、訪問者に安心感と信頼を与え、Googleからも「価値のあるサイト」として高く評価されます。
つまり、サイト構造の設計こそが、デザインや文章を支える“骨格”であり、長期的な集客・成果の安定を左右するのです。
構造とは、単に「トップ → 下層ページ」というナビゲーション構成のことではありません。
グルコムが考えるサイト構造設計とは、次の3要素で成り立っています。
トップページ、サービスページ、導入事例、会社情報、コラムなどの全体構成を整理し、どの情報をどの階層に置くべきかを戦略的に設計します。
ユーザーがサイトを閲覧する順序を想定し、「理解 → 共感 → 信頼 → 行動」へと自然に導く流れを作ります。
関連するページ同士を適切にリンクで結び、検索エンジンがサイト全体を正しく評価できるようにします。
この3つがバランスよく設計されているサイトは、制作後も更新・運用がしやすく、時間の経過とともに検索順位・アクセス数・問い合わせ数が安定して伸びていきます。
内部SEOとは、“サイト内部を検索エンジンが理解しやすく整えること”です。
外部リンク対策よりも継続的かつ長期的に効果を発揮し、正しく設計されていれば、広告費をかけずに見込み客を増やすことが可能です。
以下に、内部SEOの中でも特に重要な基本要素を挙げます。
検索結果に表示されるタイトルと説明文は、ユーザーが最初に目にする“看板”です。
単なるページ名ではなく、「誰に・何を提供するページか」が明確に伝わるタイトルを設定することが重要です。
(例)
悪い例:「製品紹介」
良い例:「中小製造業向け 高性能接着技術|製品ラインアップ」
ページ内の構造を分かりやすく伝えるために、見出しタグ(H1〜H3)は“階層構造の整理”として非常に重要です。
Googleは見出しの使い方からページ内容の主題を判断しています。
H1はページ全体のテーマを示し、H2・H3で細かいトピックを整理する構成が理想です。
パンくずリストはユーザーが現在どこにいるかを示すだけでなく、検索エンジンにサイト構造を正しく伝える役割も果たします。
また、関連ページへの内部リンクを適切に設置することで、クローラーの巡回効率が上がり、「評価がページ全体に分散せず、ドメイン全体のSEO効果が向上する」メリットがあります。
1ページに複数のテーマを詰め込みすぎると、検索エンジンもユーザーも内容を正確に理解できません。
そのため、1ページ=1テーマを意識し、各ページごとに目的・ターゲット・キーワードを設定することが大切です。
これにより、検索キーワードの一致精度が高まり、狙ったターゲット層からのアクセスを獲得できます。
このような内部SEOの基本を、制作段階からしっかりと組み込んでおくことで、Googleからの評価が安定し、時間の経過とともに“自然検索(オーガニック流入)”が伸び続けるサイトを実現できます。
グルコムでは、デザインやテキスト制作に入る前に必ず「SEO設計+情報設計」の工程を行います。
これは、単なる“SEO対策”ではなく、成果を出すための戦略的設計プロセスです。
クライアント企業のビジネスモデル・顧客層・競合分析をもとに、「どのキーワードで検索されたいのか」「どんな導線で問い合わせにつなげるか」を定義し、サイト全体を“成長し続ける集客基盤”として設計しています。
その結果、リニューアルから半年〜1年で自然検索からの問い合わせが増加した事例や、SEO広告を減らしても安定して新規リードを獲得できる企業が多数生まれています。
サイトの“構造”と“SEO設計”は、制作後の集客力・成果の持続性を左右する最重要要素です。デザインよりも先に、「どんな情報を、どんな順序で、誰に届けるか」という構造的な視点を持つことが、BtoBサイト成功の鍵になります。
グルコムは、こうした戦略的なサイト設計を通じて、企業のホームページを“営業部門の一員として機能するデジタル資産”に進化させています。
ホームページ制作会社を選ぶ際、多くの企業が「デザインの好み」や「価格」で比較してしまいます。
しかし本当に見るべきポイントは、“戦略設計をどこまで行ってくれるか”です。
・制作前にヒアリング・戦略提案がある
・SEO・導線設計・運用を含めて提案できる
・「納品して終わり」ではなく、成果を追う姿勢がある
BtoBサイトは、制作後にどれだけ成果を出せるかで真価が問われます。
パートナー選びの時点で、この視点を持つことが成功への第一歩です。
・会社紹介資料(事業内容・強み・沿革)
・顧客リストやターゲット像の整理シート
・現在のアクセスデータ・問い合わせ分析資料
これらを事前に用意しておくと、制作会社との打ち合わせがスムーズに進み、質の高い設計提案を受けられます。
見た目が良いだけでは成果は生まれません。
訪問者が「自分に関係のある情報がある」「信頼できる会社だ」と感じるための情報構成・設計こそが重要です。
成果を出しているBtoBサイトの多くは、伝える順序・導線・SEO構造のすべてが緻密に設計されています。
「制作前に設計を考える」ことが、後悔しないサイトづくりの最も大切な一歩です。
「ホームページはあるけれど、思うように問い合わせが来ない…」
「どこを改善すれば成果につながるのか分からない…」
そんなお悩みをお持ちの中小企業さまに、グルコムは戦略設計 × 内部SEO × 集客導線設計の3つの視点から最適な改善策をご提案しています。
まずは、現状のサイトを一緒に見直してみませんか?
・現状サイトの無料診断
・改善ポイントの提案
・成果を生むための戦略構成提案
企業の強みを最大限に引き出し、“営業が働くホームページ”を一緒に設計いたします。
お気軽にご相談ください。(BtoBサイト制作・リニューアルに関するご相談はこちらから)

18年900サイト以上の実績があるウェブマーケティング・制作会社。
集客から見込み客の開拓・既存客との関係構築・維持、土台であるウェブ制作まで、一気通貫できる視野・サービスを提供できることが強み。サービス紹介ページはこちらから